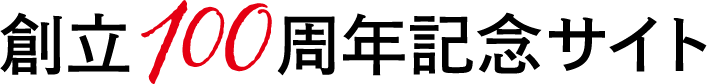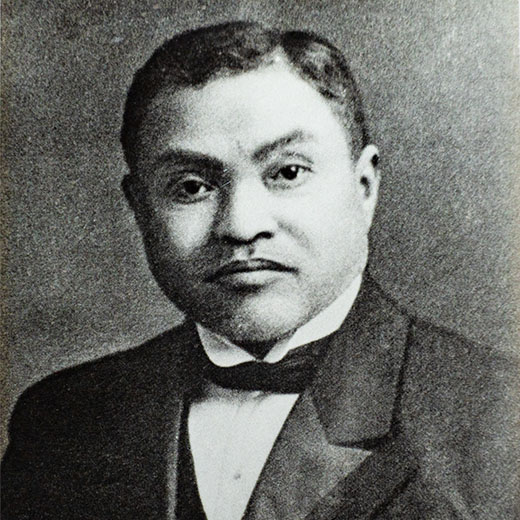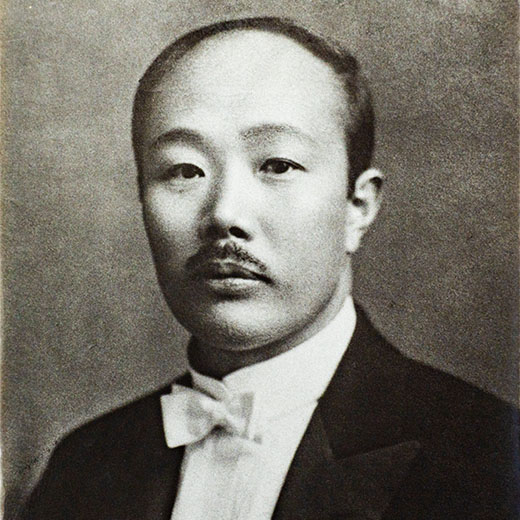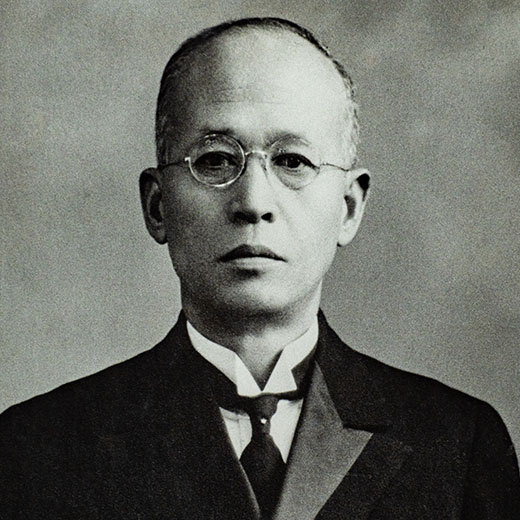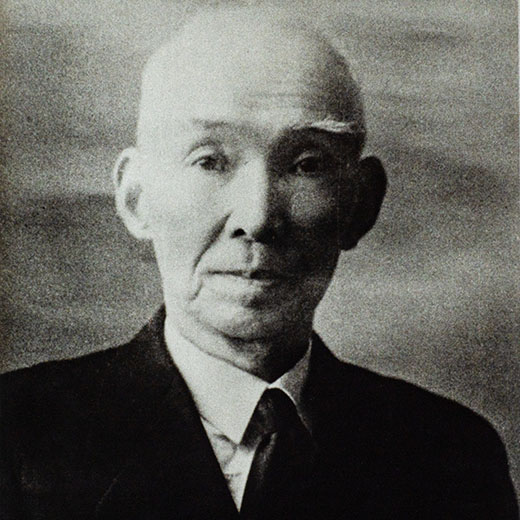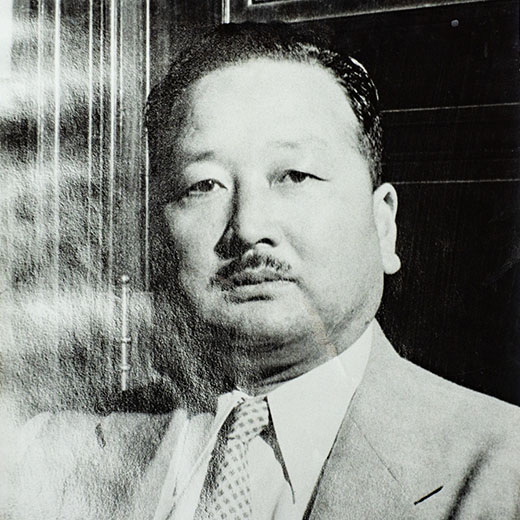荒野から経済県都へ
― 郡山のあゆみ
安積開拓から始まった郡山の発展
明治初期、荒野だった安積原野に旧藩士たちが入植して開拓を進めました。郡山の発展の鍵となったのは、奥羽山脈を越えて猪苗代湖から遠く離れた郡山へ水を引くという、壮大な「安積疏水事業」です。オランダから派遣された技術者ファン・ドールンの指導のもと、ダイナマイトや蒸気ポンプなど西洋の最新土木技術を用いて工事が進められました。明治15年、延べ85万人の労力と約3年の工期を経て安積疏水が完成。水が通ったことで、郡山は交通と産業の拠点として、人々が安心して暮らせる都市へと変わっていきます。
そして飛躍的な経済発展へ
戦後の復興とともに駅前を中心に開発が進み、商店街や百貨店が次々と誕生しました。昭和40年代には大型店が立ち並び、スーパーや専門店も増え、買い物を楽しむ人々で街はにぎわっていきます。商業の活性化は市民の暮らしに豊かさをもたらし、工業やサービス業などの産業も次第に発展していきました。郡山商工会議所もまた、組合の設立や団地の整備、さらに当時としては先進的だった「販売士制度」の教育などを通じて、地域産業を力強く支えていきました。
今から約200年前の江戸時代、宿場町として栄えていた郡山宿には約3,900人が暮らしていましたが、明治の「安積開拓・安積疏水事業」や戦後の復興、商業と産業の発展を経て、現在の約31万8千人が暮らす経済県都へと発展を遂げました。